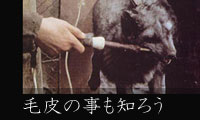日本の毛皮生産 過去と現在
毛皮自由化のあと、海外から安いなどの毛皮が入り始め、日本国内の毛皮農場のほとんどは自然淘汰的に減り続けました。
2016年、新潟でミンクを生産していた最後のミンク企業は廃業しました。
代わって、現在では海外から毛皮製品が輸入され、購入・使用されています。
データ(1例):
2017年のデータでは、うさぎは愛玩用以外に8046羽生体で、毛(うさぎ毛)も、輸入されています。生体の目的は不明です。愛玩用以外ということなので、食肉用か実験用かその他の用途かと推測できます。
軍人さんに着る物を提供するために毛皮農場が拡大し、飼育してた犬猫も国へ提供するよう命令された
日本の毛皮産業は、世界で起こった戦争および日本自身が関係した戦争の中 (1894日清戦争、1904日露戦争、1914第一次世界大戦、1937日中戦争、1941太平洋戦争) で、海外への輸出(海外の軍用)および日本の軍の需要を満たすために、市場が形成され、世界そして日本で発展してきました。戦争中は、飼っている犬や猫は国が持っていってしまいました。 軍人の方の防寒具にするため、犬や猫は殺されました。
1870年代から1985年位の約100年強の間で、日本の毛皮産業が確立し、繁栄し、そしてすたれていきました。国内の毛皮生産がすたれていく頃、海外の毛皮の輸入が増加しました。
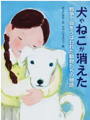 戦争ノンフィクション 犬やねこが消えた
戦争ノンフィクション 犬やねこが消えた
戦争では、多くの犬やねこもぎせいになった。ひきさかれた人と動物の悲しみの記憶を求め歩いた著者がたどりついた事実とは…。第二次世界大戦の末期に本当にあった、飼い犬や飼いねこの「供出」のお話。
著者 井上 こみち (文),ミヤハラ ヨウコ (絵)
2008年8月 学研教育出版

 ●映画 犬の消えた日: 「犬の供出」あなたのペットの命を国に捧げるということ
●映画 犬の消えた日: 「犬の供出」あなたのペットの命を国に捧げるということ
日本各地で発せられた国民への命令「飼い犬、飼い猫を供出せよ」
供出の主たる目的は毛皮の調達。
●絵本 ムツと私:戦争時代、犬のムツを、毛皮のために国に渡した大和田さんの体験を絵本にしたものです。
周りにいる野生動物をかることから始まった
最初は野生動物が狩られ、数が減り始めると、動物を飼育する方法に変えました。戦争時、国主導で毛皮調達の仕組みが確立され、その流れの中で、全日本猟友会の元となる「猟友会」が1929年に設立されました。また小学校校庭でのウサギ飼育は1920年代、国の需要を満たすために始まり、飼育されたウサギは毛皮業者へ渡され、学校はウサギ売買で得たお金を経費に回していました。また鳥獣保護法は、もともとの狩猟法が1963年に、捕り尽くしてしまうと持続的に獲り続けることができなくなることを認識し、その名称を改正したものです。
日本で毛皮目的で殺されてきた動物は、最初は野生生物である、クマ、イタチ、オコジョ、カワウソ、、ヌートリア、カモシカ、チンチラ、そして羊、たぬき、きつね、ミンク、うさぎなどでした。
乱獲によりこれら動物の数は減少しはじめました。一例については下記、ラッコ、アザラシをご覧ください。
毛皮用にミンク、キツネの飼育が始まった
野生生物の数が減少しはじめると、飼育して毛皮にするように変化がおこり、その動物として飼育が簡単なウサギとキツネの養殖がまず始まり、少し遅れてミンクの養殖が始まりました。養殖のうち、 特にウサギは農家の副収入源として盛んになりました。毛皮専業と兼業の比率は6:4でした。他の動物なども毛皮農場を試しましたが、毛皮の質が悪い、飼育が難しいなどの理由で断念されました。最盛期は400以上のミンク農場、きつね飼育戸数は3000戸以上ありました。昨今、中国でたくさんのキツネ、ミンク、タヌキが毛皮のために殺されていますが、それはまさに過去の日本の毛皮産業の再現のように見えます。
海外への輸出が始まる
1870年代、毛皮のため動物をたくさん殺し、その数が減り始めていた欧米へ向けて、外貨獲得のため、日本は毛皮の輸出を奨励します。1880年代、軍用に毛皮を調達する国レベルの毛皮調達の仕組みが開始されます。1890年代、海外への毛皮の輸出が始まります。1900年代、毛皮の市場が形成されていきます。1910年代、毛皮産業のバブル期をむかえ、農家の副収入源としてのウサギ飼育が奨励されます。イタチだけで、1913年から1922年の10年間に海外へ輸出されたイタチの毛皮だけで260万枚以上。
1920年代、ウサギ、きつねが順番に次々と養殖が開始されます。1928年、ミンクは海外から移入されました。1930年代、たぬきとヌーとリアの養殖が開始されます。1936年ごろ、うさぎの毛皮は年間、100万枚以上集められました。1940年代頃がうさぎの生産のピークで120万匹が飼育されており、この頃、うさぎ毛皮等配給統制規則ができ、毛皮用ウサギ緊急増殖措置がとられました。
ニホンカワウソ絶滅
1940年代、国内毛皮需要はピークを迎えます。また乱獲されたニホンカワウソが絶滅します。1950年代、イタチの毛皮がブームになります。1950年代、ミンク養殖が開始されます。1961年、毛皮の輸入が自由化されます。
中国から安い毛皮を輸入
自由化され、中国から安い毛皮が入るようにない、毛皮の輸入が増え、再び毛皮はブームになりました。輸入額は1984年が輸入のピークで、663億3600万円。輸入は、その後1997年ごろまで減少し続けましたが、1997年より輸入額はぶり返しています。輸入は、大半が中国。
動物の種類にもよりますが、香港、韓国、イタリア、フランス、フィンランドなどから輸入しています。現在、中国では少し前の日本のように、毛皮の大ブームがおこっているようです。
1986年の日本の毛皮動物単価の大暴落 (キツネが4万円から1万円、ミンクが7千円から4000円) が一番の理由、さらには中国から安価な毛皮が輸入され始め、餌の雑魚が入手困難、などの理由で、1986-1993年位の間にほとんどの毛皮農場が閉鎖しました。現在、日本にはわずか数軒の毛皮農場があるだけとなっています。
日本では今でも毛皮製品が売られている
1870年ごろから日本において毛皮のために多く殺されだした動物たち。140年以上経過した今でも、街のあちこちで毛皮製品が普通に販売されている国、それが日本です。日本で、最も多く動物が殺されていた頃、日本には動物の権利団体が存在せず、反対運動もありませんでした。現在なお、毛皮の現実ことを知る人は全体の人口からみれば一握りしかいません。”毛皮を着ない”という選択をし、毛皮のことを人に伝えてください。
かつてはオークションがありました。
ミンク・キツネの生産者 (農家/業者) - 農協・生産者組合ーオークション(札幌)*ー原毛皮問屋ー毛皮製造業(なめし)-製品製造卸売業ー製品小売業尾者ー消費者
現在では農業組合(ミンク農業組合)はなくなっています。
(*)以前はキツネ・ミンク毛皮のオークション機関は日本に4 社、全て北海道札幌にありました。4社とは3企業と農協が1社。現在、その農協はなくなっています。
北海道での毛皮生産:
日本ではミンク、きつねの毛皮生産については、全体生産量の90%-95%が北海道で生産されてきました。そのため、紋別、根室、釧路、札幌、網走、美唄、室蘭、温根湯、函館、さらに樺太(サハリン)など、北海道いたるところに、ミンク・きつねを飼育する毛皮農場がありました。鹿部などでは、公営の毛皮農場もありました。
その毛皮産業の繁栄のあとが現在でも見られます。
2005年、室蘭では毛皮農場から逃げ出し野生化したミンクが増えたことを問題とし、有害鳥獣として駆除を開始することがきまりました。
2007年、北海道の釧路-鶴居村間の、あるミンク農場でミンクときつね(シルバーフォックス)がいたことが旅行者により確認されています。
2008年の時点では、北海道には、紋別の遠軽町に1件あり、それ以外にはあっても1-2軒ではないかと思います。
東北、九州、本州での毛皮生産:東北の各県、宮崎県延岡市、熊本県阿蘇郡、新潟県田上市、そのほかの多くの町などに、毛皮農場がありました。
2008年の時点では、新潟県に1軒あります。2006年の工業統計などを見ると、毛皮産業者は埼玉県、奈良県、大阪府、新潟県、北海道などにあったようです。
2006年の状況
毛皮製造業(2006年) -事業者数:4、従業員数28、製造品出荷額/生産額は2億5千万円、原材料額4千700万円 (工業統計2006年版 従業者4人以上) 。なめしは含まれてません。生産額にして2億5千万円相当の動物が殺されたことを意味しています。動物の単価がわかりませんが、1頭1万円とすれば約5000頭、単価5千円とすれば、約1万頭が殺されたことになります。
2006年の従業者数4人以上の工業統計などからわかるのは、毛皮製造業者は、埼玉県と新潟県、大阪府、奈良県などにあるようです。実際にインターネットで検索しても、それらしい毛皮農場があります。工業統計には従業者4人以下の毛皮製造業の数字がありませんが、文献をみると、過去には、従業業者数4人以下の個人経営形態でも、ミンク飼育数300-500頭の中規模~1000頭を飼育する者も少なからず存在します。4人以下の個人経営の農家を含めると、事業者数、従業員数はこの数字よりも多い可能性があります。
だんだんと衰退
ここ直近の30年程を見ると、日本市場においては、、1984年ごろをピークに市場規模(小売価格換算額)は縮小し続け、1997年で底を打ちます。(1997年の小売価格換算で504億円、ピーク時の5分の1をさらに少し下回る数字です)。減少原因は、単価の低下、地球温暖化、欧米で動物愛護が活発になったこと、などです。
低迷を続けたあと、1997年より以降、市場規模は拡大を再度続け、2001年では1980年ごろの半分ぐらいまでぶり返しました。小売換算額で1176億円です。その後現在まで1000億円強で推移しています。日本国内での毛皮農場の数が増えていないことを考えると、国内産毛皮が全部輸出ではないとすれば、少数の国内毛皮および輸入された毛皮を大量に消費していることになります。
最近では、毛皮のコートより、毛皮が他の素材と一緒に、服や雑貨の一部として使われていることが多く、その場合は、服の場合にはアパレル製品としての扱いになり、毛皮の数字にはのってきませんので、市場規模は実際にはこれよりも大きいと考えられます。
餌は以前は主に、クジラ肉類が使われていましたが、鯨肉が入手しにくくなると、家畜からでる廃棄物 (=血液、肺などの内臓)、魚などが餌して使われました。北海道でまず、毛皮生産が盛んになった理由は、これらの餌を調達しやすかったからです。
北海道以外で毛皮生産が盛んだった都道府県はイルカ猟、捕鯨をしている県とかなりだぶっています。理由は、北海道の場合と同じではないか、つまり餌であるクジラ肉類、家畜からでる廃棄物(血液、肺などの内臓)、魚を入手しやすかったからではないかと思われます。
鯨肉を毛皮用養殖動物であるきつねやミンクの餌として利用してきたのは、日本に限りません。歴史的に毛皮の最大の生産国の一つであるロシアでも、鯨肉が餌として使われていました。そして、その鯨肉は、”原住民生存捕鯨”を理由にIWCより認められた捕獲枠で獲った鯨であり、捕獲された鯨の半分以上の肉がロシアの国営のキツネ農場の餌として使われています。IWCがこれを問題にしないことについて、日本の捕鯨をする人たちから非難されています。
日本で毛皮目的で殺されてきた動物は、最初は野生生物である、クマ、イタチ、オコジョ、カワウソ、、ヌートリア、カモシカ、チンチラ、そして羊、たぬき、きつね、ミンク、うさぎなどでした。
乱獲によりこれら動物の数は減少しはじめたため、きつねやミンクなどを毛皮用に飼育するようになったのです。その一例をあげます。
今から100年と少し前、日本政府はラッコやオットセイの捕獲を奨励し、日本近海でラッコはほぼ絶滅しました。
乱獲により絶滅。明治政府が保護法を作るが時すでに遅し。
明治政府は、「臘虎膃肭獣猟獲取締法」という動物保護法を作り、ラッコなどを保護しようとしたが、すでに乱獲され、数が戻ることはありませんでした。
時代の流れの中、日本では自然に毛皮目的のアザラシ猟はなくなりました。
最盛期は年間2500頭ほど捕獲 (wikipediaより)
日本では古くからアザラシ猟が行われてきた。北海道の先住民であるアイヌ民族や開拓期の入植者も利用した。 皮は水濡れに強く、馬の手綱やかんじきの紐に好んで使われた。また脂肪は照明用に燃やされた。 昭和以降になると皮がスキーシールやかばんの材料になったり、脂肪から石鹸が作られたりした。 昭和30年代以降はみやげ物の革製品の材料として多く捕獲された。この頃になると猟も大規模になり北海道近海からサハリン沖にまで及んだ。最盛期の年間捕獲頭数は2500頭ほどと推定されている。 その後、環境保護の流れが盛んになりファッションの材料としての需要の低迷、ソ連の200海里水域経済水域宣言、輸入アザラシ皮の流入等の理由により昭和50年代には商業的なアザラシ猟は終わりを迎えた。 現在では北海道の限られた地域で有害獣駆除を目的としてわずかな数が捕獲されているのみである。
最盛期ごろは、きつねの飼育業者全てが、ミンク飼育と兼業していました。
■日本の養殖キツネ農場の歴史
1915年、樺太小沼の農事試験場できつね (赤きつね、十字きつね) の飼育開始。その翌年、当時の農商務省が、中部千島できつねの飼育を開始したことが始まりです。
1920年から1940年ごろまでの間、日本国内のキツネ毛皮生産数はうなぎのぼりに増え続けました。多くの組合ができ、重要な産業として発展してきました。1940年には3000戸の飼育業者(農家)があり、30000枚の毛皮が生産されていました。
■日本の養殖キツネ農場数
毛皮農家(業者)は、北海道紋別の遠軽町に1軒、新潟県に1軒あります。それ以外では、インターネットおよび工業統計からみると、蔵王、埼玉県にあるように推測されます。そちらでミンク以外としてキツネも飼育しているかは不明ですが、2007年、北海道の釧路-鶴居村間の、あるミンク農場でミンクときつね(シルバーフォックス)がいたことが旅行者により確認されています。
以前 (1941)は飼育業者3,000戸、キツネの数 15,000頭(種類は銀狐、青狐、プラチナ狐、ホワイトフェースなど)、きつね毛皮生産 3万枚強というデータがあります。
■日本のきつね毛皮生産量
1976年 3000枚の毛皮が生産される。ほとんどが銀キツネ、1割弱が青キツネ、プラチナキツネとホワイトフェースはそれぞれ数パーセント(100頭)前後。
■きつね屠殺
・1月ー12月を1サイクルとする。
・春 (3月頃)交配させる。
・初夏 (5月ごろ)赤ちゃんが生まれる。
・夏 子育てさせる。ジステンパー、脳炎などの各種ワクチン接種。
・秋 (9-10月)換毛期
・冬 屠殺時期 剥皮期 オークション、屠殺、農協などに出荷
・皮剥ぎ: 殺したあとすぐ、体があたたかいうちが、毛皮を剥ぎやすいため、殺してすぐに皮をはがします。また、血が毛につかないように注意してこの作業は行われます。
■殺し方
感電しさせ殺す方法、毒殺、拘束器具 (叉木 = 頭部を木に拘束する。高さの低い木製のギロチンのようなもの) による圧殺して殺す方法があります。
毒物による殺し方は、硝酸ストリキニーネを溶かした毒液を注射して毒殺する方法。電気ショックは、拘束器具(叉木)にキツネをいれ、口と肛門に電極を入れ10秒以上電気を流し、感電死させます。
叉木による圧力殺方法とは、木の間にキツネの首を入れ圧迫して圧死させる方法です。
■日本の養殖ミンク毛皮農場の歴史
1928年に北海道にミンクが初めて連れてこられる。その後1953年に アメリカからミンクを輸入して毛皮用に増やしはじめたのが始まりです。
■日本の養殖毛皮ミンク農場数
1950年代から1980年頃までがミンク農場がたくさんあった時代です。
2016年、新潟でミンクを生産していた最後の生産者の方は2016年に廃業しました。かつて紋別でミンク毛皮農場を経営していた企業は現在(2020年)も存在しますが、2002年から毛皮の原料の輸入を開始し、毛皮製品を制作販売しています。
日本で毛皮農場があった頃は、日本産のミンクが海外のオークションにも出品されていました。
以前は、1978年では約80戸、1982年では約170戸ほど存在した。 内訳は下記。
- 飼育数300頭以下が30%
- 飼育数300-500頭が約30%
- 飼育数500-1,000頭が約20%
■日本のミンク毛皮生産数
1982年: 頭数は約90万匹が飼育され、国内で約66万枚のミンク毛皮生産高でした。
このころが最盛期で、その後は毛皮農場も減り、数千枚以下と推定されています。
■ミンク屠殺
・1月ー12月を1サイクルとする。
・春 (3月頃)交配させる。
・初夏 (5月ごろ)赤ちゃんが生まれる。
・夏 子育てさせる。ジステンパー、腸炎、アリューシャン病などの各種ワクチン接種
・秋 (9-10月)換毛期、この時期、アリューシャン病検査(ヨード反応)
・冬 屠殺時期 剥皮期 オークション、屠殺、出荷
・ミンクの種類により、11月初旬~11月中旬から殺し始める。
・皮剥ぎ: 殺したあとすぐ、体があたたかいうちが、毛皮を剥ぎやすいため、殺してすぐに皮をはがします。また、血が毛につかないように注意してこの作業は行われます。
■殺し方
日本で行っていた殺し方は、首の骨を折る方法(頚椎脱臼)と、劇薬を使って殺す毒殺です。
毒殺は硝酸ストリキニーネを溶かした毒液を注射し毒殺します。
日本で毛皮用に飼育されていたミンクの種類
世界的に数が少ない毛色がブルー系のサファイアが、約半分
世界的にはほとんどがこの毛色であるデミパフ、パステル、ダークはそれぞれ10%でこれらの合計で30%。
こちらのサイトにたどり着いた方へご協力をお願いします
Twitter, FacebookなどのSNSや、お持ちのブログやサイトでこちらのサイトを広めていただければ幸いです。